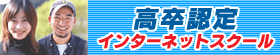公共の攻略法・傾向と対策/高卒認定【高認】
01/04
高卒認定試験「公共」の概要
| 試験時間 | 50分 |
|---|---|
| 問題数 | 全24問(5つの大問で各4~5問) |
| 解答形式 | すべて選択式(マークシート・4択) |
| 合格予想点 | 40点 |
| 出題傾向 |
|
02/04
高卒認定試験「公共」の出題傾向
出題形式と特徴
- 全てマークシート方式
- 会話文や資料文、グラフや図表を読み取って答える問題が多い
- 「暗記」だけでなく、資料から根拠を見つけて判断する力を重視
これまでの出題例
- 青年期・自分らしい生き方
- ヤマアラシのジレンマ、フランクル、サルトルなどの思想
- 倫理と社会の基本原理
- 功利主義・義務論、正義や公正の考え方
- 法と人権
- 民事・刑事裁判の違い、裁判員制度、消費者保護制度
- 政治制度と地方自治
- 国会の役割、選挙制度、住民参加制度
- 経済・雇用・国際社会
- 為替、貿易、社会保障制度、国際経済
- 環境・SDGs
- 脱炭素、再生可能エネルギー、国際的な環境対策
03/04
高卒認定試験「公共」の試験対策
高校の公共は、社会の仕組みや課題を知り、自分の考えを持って行動できるようになるための科目です。高卒認定試験の公共では、その知識を土台に「資料を読み解き、判断する力」が問われます。暗記だけでなく、「なぜそうなるのか」を意識して学ぶことが、合格への近道です。
学習のポイント
1・会話形式・資料問題への対策(資料読解に慣れる)
- グラフや統計、会話文から必要な情報を素早くつかむ練習をする
- 問題文に登場する会話のやりとりから「立場」や「背景知識」を正確に読み取る訓練を
- 図表やグラフの読み取り力をつける(割合・推移・比較)
2・語彙と用語の整理(キーワード理解)
- 「立憲主義」「公共の福祉」「法の支配」「自然権」「多文化共生」「ノーマライゼーション」などよく出る言葉は意味を説明できるように
3・現代社会のニュースや時事にも触れる(時事問題もチェック)
- 少子高齢化、女性の政治参加、国際的な安全保障、環境問題などは時事問題として出題傾向強め
- 新聞やニュースの要点を見出しだけでもチェック
04/04
高等学校で学ぶ「公共」と高卒認定試験
「公共」は、高校の「公民」の必修科目で、社会の中で自立した主体として生きるために必要な知識や考え方を学びます。学習内容は大きく3つの分野で構成されており、1→2→3の順にステップアップしながら学びます。各分野は相互に関連し合い、知識と考え方を積み重ねていく構成になっています。
以下の【 】は便宜上の分野区分です
1・公共の扉【倫理分野】
最初のステップは、「社会の中で自分はどう生きるか」を考える入り口です。日常生活や学校生活での出来事から、自分と社会のつながりを意識します。たとえば、SNSでの発言、学校行事での話し合い、地域でのボランティア活動など、身近な場面と直結しています。
- 公共的な空間と人間の関わり
私たちは一人で生きているわけではなく、家族・友人・地域・国など、多くの人や組織とつながって暮らしています。 - 生き方と価値観の探求
自分の考えや価値観を大切にすると同時に、他の人の意見や背景も理解しようとする姿勢が大切です。 - 倫理的判断の基礎
「みんなが幸せになるには?」(功利主義)や「ルールや約束は守るべき?」(義務論)など、考え方の違いを学びます。 - 共的原理の理解
憲法や民主主義、法の支配など、社会の土台となるルールや基本原理について理解を深めます。
高卒認定対策「青年期・自我の形成と人間の在り方」
●出題例
- ヤマアラシのジレンマ、ヴィクトール・フランクル『夜と霧』
- サルトルの実存主義
●対策
- 「自分らしさ」「生き方」などのテーマに関する哲学・倫理思想(実存主義、人間観など)を簡単にでも押さえておく
- 青年期の心理的特徴や発達課題も重要
高卒認定対策「現代の社会と倫理・政治思想」
●出題例
- 功利主義(最大多数の最大幸福)と定言命法
- 思いやりや仁(儒教的倫理)などの徳倫理
●対策
- 倫理や政治哲学の基本的概念(功利主義、立憲主義、法の支配)を整理
- 異なる立場や価値観から物事を考察する練習をする
2・自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち【政治・経済分野/国際社会分野】
次のステップでは、社会の仕組みやルールを理解し、現実の課題にどう関わるかを考えます。自分の生活や将来に直結するテーマについて、他者と協力して意見をまとめる練習も行います。たとえば「アルバイト先の労働条件」「選挙に行く理由」「税金の使い道」などが題材になります。
- 法の役割と権利保障
契約や消費者トラブル、裁判員制度など、トラブルを公平に解決する仕組み。 - 政治参加と民主主義
選挙や地方自治、国の安全保障や国際協力など、意見を反映させる方法。 - 経済と社会保障
働き方やお金の流れ、税金や社会保障、景気や貿易など、生活を支える仕組み。
高卒認定対策「政治制度・国会・地方自治」
●出題例
- 衆参両院の役割、予算・法律・条約の扱い
- 男女共同参画・政治参加意識の年齢別違い
- 地方自治と住民の直接請求
●対策
- 衆議院・参議院の違い、選挙制度(小選挙区・比例代表など)の基礎を理解/li>
- 地方自治の制度や住民参加(条例制定・議会解散請求)も確認
高卒認定対策「経済・雇用・労働・国際社会」
●出題例
- 為替相場・貿易・FTA(EPA)と国内産業の関係
- 雇用制度(最低賃金・年功序列・ワークライフバランス)
- 国際投資・金融(直接投資/証券投資)
●対策
- 基本的な経済用語(GDP・インフレ・円高円安など)をおさえる
- 社会保障制度・労働問題・格差や少子高齢化の対策なども実感をもって学習する
3・持続可能な社会づくりの主体となる私たち【環境・SDGs分野】
最後のステップは、「未来の社会をどう作るか」を総合的に考え、行動につなげる段階です。地域から世界まで幅広い課題に目を向け、解決策を考えます。自分の提案や行動が、社会をよりよく変える第一歩になることを学びます。
- 地域の課題(例:過疎化や防災)、国の課題(例:少子高齢化や経済)、世界の課題(例:気候変動や貧困)を取り上げます。
- SDGsのように、国際的な協力が不可欠な問題にも取り組みます。
- 課題を見つけたら、「どんな方法なら実行できそうか」「どんな効果があるか」を考え、根拠をもって説明できる力を養います。
高卒認定対策「地球環境・持続可能な社会(SDGs)」
●出題例
- CO₂排出・再生可能エネルギー・木造ビル
- 炭素税・排出量取引・気候変動対策
●対策
- 温暖化防止の国際的枠組み(パリ協定など)
- 炭素税・グリーン成長・カーボンニュートラルの用語理解
- SDGs17目標も目を通しておくと良い