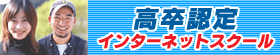物理基礎の攻略法・傾向と対策/高卒認定【高認】
物理基礎の選択について
物理は、力やエネルギー、熱、波、電気などを扱います。これらは目に見えないためイメージしにくい概念です。物理の学習は他の科目と比べて難しく、短期間で実力を身につけることは難しい科目です。さらに、数学的な知識や理論的な考え、センスも必要で、まさに理系の代名詞ともいえる科目です。物理を好んで勉強しない限りは、実力を伸ばすことは難しいかもしれません。
ただし、物理の実力を身につけるには時間がかかりますが、その分、安定した実力が身につきます(=一度身についた実力は落ちることはあまりない)。そのため将来、理工系の大学に進学したい人は早くから勉強しておくという方針(作戦)で、物理基礎を選択するのも懸命でしょう。
その他、特別な理由がない限りは、高認での物理の選択は避け、他の理科系科目(科学と人間生活、化学基礎、生物基礎、地学基礎)を選ぶことをおすすめします。
試験の出題傾向と対策
物理基礎の試験範囲は、次の表のとおりです。例年は20問出題され、特に「力の表し方」「様々な力とその働き」「力学的エネルギー」の分野が多く出題されます。この3つの分野は関連しているので、勉強するときは、1つの分野のイメージで勉強するとよいでしょう。また、実生活の現象や簡易実験の設定を用いた問題が頻出で、図やグラフ、計算も多く登場します。過去問で慣れておくとよいでしょう。
| 項目 | 試験内容 |
|---|---|
| 運動の表し方 | 速度と加速度、等加速度直線運動、落下運動、速度の合成、相対速度 |
| 様々な力とその働き | さまざまな力(重力、摩擦力、弾性力など)、作用・反作用の法則、力の合成・分解とつりあい、運動の3法則、運動方程式(斜面上の運動、連結した物体の運動など)、物体の落下運動 |
| 力学的エネルギー | 仕事、仕事率、摩擦力(静止摩擦力、動摩擦力)、運動エネルギーと位置エネルギー、弾性エネルギー、力学的エネルギーの保存 |
| 熱 | 熱運動、セルシウス温度、絶対温度、熱と温度、熱量、熱平衡、潜熱、比熱、熱容量、熱量の保存、熱膨張、熱と仕事、内部エネルギー、熱力学の第1法則、さまざまなエネルギーの移り変わりとエネルギーの保存、熱機関と熱効率(可逆変化と不可逆変化)、気体の圧力、大気圧 |
| 波 | 波の要素(正弦波と波、振幅、波長、周期、振動数、媒質の振動など)、横波、縦波、波のエネルギー、重ねあわせの原理、波の独立性、定常波、波の反射、固定端反射、自由端反射、音波の性質や伝わり方(音の速さ、音の3要素、音の反射、うなりなど)、物体の振動(共振、共鳴、弦の固有振動、気柱の共鳴など) |
| 電気 | 電荷、摩擦電気、静電気力、電流や電圧、オームの法則、ジュールの法則、電力と電力量、物質と電気抵抗、電気の利用 |
計算問題が多くあります。問題は基礎レベルですが、(高認の)数学と違って、単に公式を暗記しただけでは正解は得られないでしょう。一つの現象(例えば、ボールが高い所から落ちる現象)でもさまざまな条件のもとで出題されるからです。公式はv=at(速さと加速度)、F=ma(運動方程式)、W=Fd(仕事)、P=VI(電力)などは基本です。公式を単なる公式として覚えるのではなく、なぜその公式が成り立つのかを理解した上で、公式を覚えて、さまざまな条件に正しくあてはめることができるよう勉強しておく必要があります。
例えば…
高いところからボールを静かに落とします。これは「物が落ちる(物体の落下)」という物理現象です。
この「物が落ちる」という現象には「物が落ちるときにはだんだん速くなっていく」というきまり(法則)があります。
そして、きまりには、落ち始めてからの時間と速さの関係を表す公式があります。1秒後には9.8の速さ、2秒後には19.6の速さ、3秒後には29.4の速さになります。
重いボールでも軽いボールでも同じです。公式で表すと(速さ)=(9.8)×(時間)となります。もし、5秒後に地面に落ちたとすると、地面に落ちるときの速さは、9.8×5=49の速さになります。この公式をさまざまな問題(=さまざまな条件)で使い方を練習します。
例えば、静かに落とすのではなく「投げ落とした場合」、「投げ上げた場合」、「空気の抵抗を考慮した場合」などです。
※上記文中の速さの単位はm/sです。
計算問題は、単位変換や条件整理を正確に行うことがポイントです。文章題・図解・選択肢による実験的な問題も頻出します。教科書・参考書に載っている例題を繰り返し解いて慣れておきましょう。
学習の進め方と参考書
物理を勉強する場合、分野ごとの物理現象を参考書や教科書でよく理解して、それぞれの物理現象に対応する原理やきまりや法則を正しく理解します。そして、それらに対応する公式を学び、その公式のあてはめ方を、条件が異なる多くの問題を通して練習しておく必要があります。
つまり、原理→公式→条件の使い分け→計算練習→実戦問題という順序で学ぶのが効果的です。
また、物理は目に見えない対象(力、エネルギー、波・・・)を数値化して扱います。とにかく、教科書、参考書などの例題や過去問題を数多く解いて、目に見えない対象を具体的なイメージが持てるようになるまで、十分な学習が必要です。
特に間違えた問題は、数時間後または数日後に再び解くなどの復習を徹底しましょう。
教科書をお持ちでない場合は、「高校これでわかるシリーズ(文英堂)」が高認向きで、基礎から理解したい方には「高校とってもやさしいシリーズ」もおすすめです。
過去問は特に効果的です。高認過去問集を使って、出題形式や傾向に慣れましょう。計算ミスや単位間違いがないよう、見直しの習慣も大切です。
間違えた問題は必ず復習し、数日後にもう一度解くようにしてください。
一旦実力がつけば物理は楽しくなる!
物理は最初は難しく感じますが、一度理解が深まれば安定した実力がつき、模試や本番でも得点が安定します。数式で自然を説明する楽しさを実感できるようになれば、物理が好きになるはずです。物理ほど楽しく、興味深い科目はないと感じることでしょう。